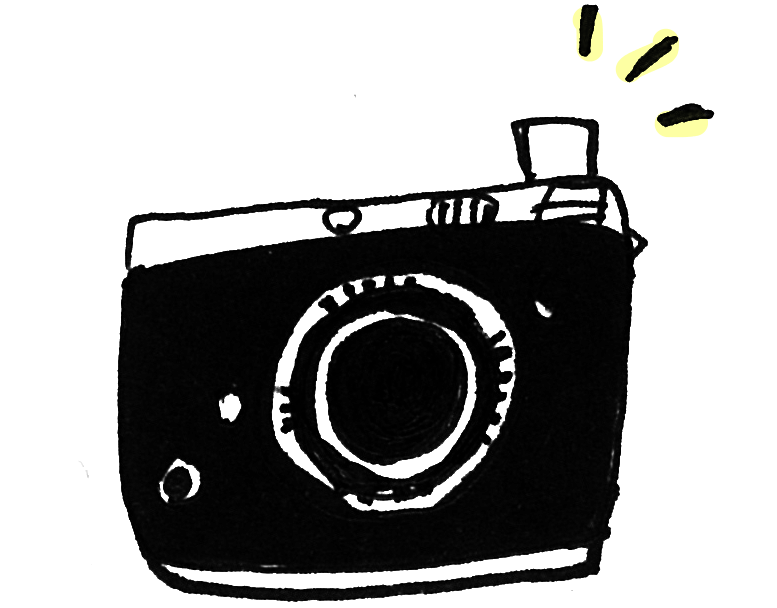
皆さんこんにちは。
令和元年ということもあり、今回はリアルその時代を生きた者にしか語れない視点から、この10年間のカメラメーカーの潮流をまとめてみます。
[目次]
- 2009年頃 〜ミラーレスの始まり〜
- 2009年頃を代表するカメラ
- 2009年頃のカメラ業界の潮流
- ミラーレスの始まりは静かに
- 判断を間違えたリコーのユニット交換式
- 2010年頃 〜将来性を感じさせるEマウントの登場〜
- 2010年頃を代表するカメラ
- 2010年頃のカメラ業界の潮流
- 未来を見据えたEマウントの誕生
- マイクロフォーサーズシステムに漂う暗雲
- 当時の各社カメラメーカー担当者との思い出
- 後発ゆえに正しい道を選べたソニー
- Aマウントの終焉を認める結果になったトランスルーセントミラー・テクノロジー
- 2011年頃 〜荒れ狂うカメラ女子ブーム〜
- 2011年頃を代表するカメラ
- 2011年頃のカメラ業界の潮流
- 一眼レフへの未練を捨てきれなかったニコンとペンタックス
- 吹き荒れるカメラ女子ブームと翻弄されたメーカーたち
- 最初から地獄だったPENTAX Qとビッグチャンスを逃したNikon 1
- 2012年頃 〜機械計測という新しい評価基準〜
- 2012年頃を代表するカメラ
- 2012年頃のカメラ業界の潮流
- カメラ女子ブームからカメラ男子ブームへ
- DxOに代表されるレビューサイトの一般化
- レンズ開発の実例にみる性能数値化の危険性
- カメラの評価に対する思想が求められる時代に
- 2013年頃 〜遂に登場したフルサイズミラーレス〜
- 2012年頃を代表するカメラ
- 2013年頃のカメラ業界の潮流
- フルサイズミラーレスの始まり
- DfとFマウントのニコンにとっての功罪
- その他のミラーレスメーカーの苦しみ
- レンズ交換式カメラが売れた最後の年
- 2014年頃 〜レンズ交換式カメラまでもがスマホの餌食に〜
- 2014年頃を代表するカメラ
- 2014年頃のカメラ業界の潮流
- 徹底改善されハイアマのフルサイズミラーレス移行を予感させたα7 II
- ユーチューバーを主体に自撮り動画需要に嵌ったLUMIX GH4のコンセプト
- 2015年頃 〜加速するソニーの技術力〜
- 2015年頃を代表するカメラ
- 2015年頃のカメラ業界の潮流
- ソニーの技術力を見せつけたα7R II
- ひっそりと動画用途でプロに広がり始めたα7R II
- 2016年頃 〜打つ手がなくなったオリンパスの凋落〜
- 2016年頃を代表するカメラ
- 2016年頃のカメラ業界の潮流
- オリンピックイヤーを飾った一眼レフの高級機達
- かつての大成功に足を引っ張られたオリンパス
- 2017年頃 〜一眼レフの到達点とミラーレスへの転換点〜
- 2017年頃を代表するカメラ
- 2017年頃のカメラ業界の潮流
- ハイクオリティを実現したD850とそれゆえに見え始めた一眼レフの到達点
- 報道用プロ機の市場に進出し攻勢を仕掛けたソニー ブルーオーシャンへ船出した富士フイルム
- 2018年頃 〜ついに登場したZとRF〜
- 2018年頃を代表するカメラ
- 2018年頃のカメラ業界の潮流
- 待望のニコン・キヤノンのフルサイズミラーレスの登場とその評価
- 悩ましいマウント径とフランジバック長の選択
- 新マウント採用を決断したキヤノン
- 2019年頃 〜ソニーの失速とタイタニックと化したカメラ業界〜
- 2019年頃を代表するカメラ
- 2019年頃のカメラ業界の潮流
- ここ数年業界をリードしてきたソニーの停滞
- 止まらないカメラ業界の衰退
- パナソニックもフルサイズミラーラレスに参戦
- 2020年以降 〜写真文化とカメラの変遷〜
- カメラ業界を救う術は…もうない。
- それでも写真文化は無くならない
というわけで今回は、2009-2019年までの10年間のカメラ業界の潮流をお話しします。
■2009年頃 〜ミラーレスの始まり〜

2009年頃を代表するカメラ
オリンパスE-620/シグマDP2/ニコンD5000/ソニーα380/ペンタックスK-7/オリンパスPEN E-P1/リコーGR DIGITAL III/パナソニックLUMIX GF1/キヤノンEOS 7D/ニコンD3S/ソニーα550/リコーGXR
2009年頃のカメラ業界の潮流
ミラーレスの始まりは静かに
現在ではレンズ交換式カメラの主流がミラーレスへと移行したものの、2009年頃のカメラ業界はまだまだ一眼レフの方が圧倒的に主流の時代で、ミラーレスがレンズ交換式カメラの主流になるという雰囲気がカメラ業界にあったわけではありません。
2008年にパナソニックから、2009年にオリンパスからミラーレス機が登場しましたが、その後しばらくは「一眼レフで生き残れないメーカーから順にミラーレスに活路を求めていった」という雰囲気で、キヤノン・ニコンもミラーレスに注目はしてはいましたが、表立ってミラーレスにそれほど危機感みせるというようなことはありませんでした。
またニコンのAPS-CフラッグシップであるD300シリーズの対抗機として、キヤノンから待望のEOS 7Dが登場し2009年で最も注目を集めた機種となりました。
発売当初は不具合などもあり特にキヤノンとニコンのファンの間で激論が交わされたEOS 7Dですが、セールス的には大成功を遂げました。
判断を間違えたリコーのユニット交換式
この年もっとも大きな失策となってしまったのはGXRで、このレンズとイメージセンサーを一体化しボディを分離するという、いわゆる「ユニット交換式システム」でリコーは大きく挫折していくことになります。
カメラファンの多くにGXRが発表された瞬間に「コレじゃない」という空気が漂ったのですが、GXRはどこに問題があったのでしょうか?
その当時のカメラマニアの中にあったシステムカメラの一つの理想形として、レンズだけでなく進歩著しいイメージセンサーを交換できる新しいレンズ交換式カメラシステム、つまり、それまでのレンズ+ボディ(イメージセンサー内蔵)という組み合わせではなく、
- レンズ+ボディ+イメージセンサー
という形のイメージセンサー分離型のカメラシステムでした。
それはある意味では中判カメラのデジタルバックと同様の構造なのですが、カメラマニアたちが期待していたのは中判のようなデジタルバック方式ではなく、「SDカードを差し込むようにイメージセンサーを差し替えることができるカメラ」というものでした。
それによって、
- 高画質な新型イメージセンサーが登場すればセンサーだけを交換できる
- 一つのボディで解像重視の際は高画素イメージセンサーに、高感度耐性重視には低画素のイメージセンサーに差し替えられる
というシステムになるというわけです。
しかしGXRのユニット交換式では、「進歩のゆるやかな(あるいは長く使える資産というイメージのある)レンズ」と「(当時)進歩の早いイメージセンサー」を一体化してしまっており、進歩の速度が最も異なるレンズとイメージセンサーという最悪の組み合わせで一体化してしまったという印象をカメラマニアに与えました。
またレンズにイメージセンサーがくっついているため、必然的にレンズが同スペックのレンズと比較して高コストになりやすいという問題もありました。
リコーとしては「イメージセンサーにゴミが付着しにくい」とか、「最適化されたレンズとセンサーの組み合わせを実現できる」といったようなことをアピールしてみたものの、少なくともそれがセールスに反映される形でユーザー側には受け入れられることはありませんでした。
またこの一部のリコーファンにさえ「誰も止める奴はいなかったの?」と言われるシステムは、リコーのカメラ開発部門の風通しの悪さを感じさせて余りあるものでした。
と言っても、そもそも「薄型ボディにSDスロットのようにボディ下部(あるいは側面)からユーザーが気楽にイメージセンサーを差し替えられる構造」というのはあまり現実的ではない上に、センサーとボディを一体で設計するメリットも大きいため、その後も「レンズ」「ボディ」「センサー」の分離型というシステムを大手カメラメーカーが採用することはありませんでした。
いずれにせよこの年もっとも大きくこけてしまったのがリコーで、このミラーレスへの進出の失敗はリコーにとって後々まで大きな悪影響を及ぼすことになります。
■2010年頃 〜将来性を感じさせるEマウントの登場〜

2010年頃を代表するカメラ
キヤノンEOS Kiss X4/パナソニックLUMIX G2/ペンタックス645D/ソニーNEX-5,NEX-3/シグマSD15/ニコンD3100/キヤノンEOS 60D/ペンタックスK-5/ソニーα55/オリンパスE-5/ニコンD7000/パナソニックLUMIX GH2
2010年頃のカメラ業界の潮流
未来を見据えたEマウントの誕生
2010年最大のインパクトを残したカメラは当然ソニーのNEX-5とNEX-3でしょう。
Eマウント機の正式発表の数ヶ月前までソニー開発者は大手カメラ系メディアなどで「α(当時Aマウントを示していた)システムはまだまだやれることがある、ミラーレスはまだ考えていない」という趣旨(※出さないと明言していたわけではありません)の発言をしていたものの、実際には裏で着々とEマウントの開発は進行していました。
ただソニーからミラーレス機、それも最低でもAPS-C(場合によってはフルサイズにも)対応したマウントのミラーレス機が登場するだろう、ということは多くのカメラマニアが予見(あるいは期待)していました。
そして時を置かずしてソニー初のミラーレス機、NEX-5とNEX-3が発売されることになります。
マイクロフォーサーズシステムに漂う暗雲
この時点で、先見の明がある人たちは「ミラーレスへのマウント移行」という絶好の機会にマウントの大型化を図れなかったマイクロフォーサーズ陣営(パナソニック・オリンパス)の衰退を予見していましたし、実際にそのようになっていきます。
パナソニック・オリンパスは一眼レフ市場でのフォーサーズマウントで苦戦しており、ミラーレスは一眼レフで生き残れないであろうメーカーの救命艇でもあったわけですから、フルサイズ機を使う人が今ほど多くはなかった時代とはいえ、マウントの将来性を考えれば当時の顧客であるフォーサーズレンズユーザーを切り捨てることになったとしても、フルサイズ対応のマウント径にすることは新マウントの絶対条件でした。
これは後出しジャンケン的な意見ではなく当時既に一部のカメラマニアからもそうした意見は出ていました。
しかし結局パナソニック・オリンパス共にマイクロフォーサーズという小舟でミラーレスという大海に漕ぎ出すことになります。
後発ゆえに正しい道を選べたソニー
対してソニーですが、ソニーはパナソニックとオリンパスにミラーレスで先行されたが故にその2社との差別化が求められ、かつ一眼レフ(※トランスルーセントミラー機も含めて)でのAマウントの生き残りが難しい状況を見通すことができていました。
そうした事情もあってかソニーはAPS-Cセンサーを採用し、かつフルサイズセンサーを搭載することが可能なEマウントを採用したことが後のソニーの大躍進へと繋がっていきます。
Eマウントは当初こそ(マイクロフォーサーズ陣営と比較して)ラージフォーマットというメリットがカメラマニア以外の一般の人たちに伝わり辛かったこと、そして何よりも当時始まっていたカメラ女子ブームによって、特に国内市場ではオリンパスの後塵を拝する時代が続くのですが、マウントの将来性という意味においてEマウントはミラーレス市場において当時圧倒的に先見の明があるマウントでした。
Aマウントの終焉を認める結果になったトランスルーセントミラー・テクノロジー
その裏でAマウントの存続のためにソニーはα55などでトランスルーセントミラー機もリリースを始めるのですが、そもそもトランスルーセントミラー・テクノロジーはアイデアとしてはペリクルミラーの焼き直しであったこと、またその機能的メリットにおいても、将来的にミラーレスシステムで代替可能なものであることは明白でした。
そのためトランスルーセントミラーをAマウントで採用したことは、必死にひねり出してきたという意味で「そういう手できたか」とは思わせたものの、明らかなAマウントの一時的な延命措置でした。
またこれはα900で散々訴えていた「光学ファインダーの魅力」というアピールに対する裏切りであったと共に、ミノルタ時代のαのセールスポイントの一つであった光学ファインダー技術をある程度捨てるという宣言でもあったため、ソニーがAマウントを(内部的には既に)諦めていて、やがてはEマウントへ主軸を移すことが誰の目にもハッキリした瞬間でもありました。
しかしそれなりの歴史もあったAマウントの(事実上の)切り捨てを行えたからこそ、ソニーは後にミラーレス市場で躍進していくことになります。
■2011年頃 〜荒れ狂うカメラ女子ブーム〜

2011年頃を代表するカメラ
キヤノンEOS Kiss X5/富士フイルムFinePix X100/シグマSD1/ソニーNEX-C3/オリンパスPEN E-P3/リコーPENTAX Q/ソニーα77/パナソニックLUMIX GX1/ニコンNikon 1 V1,Nikon 1 J1/富士フイルム X-Pro1
2011年頃のカメラ業界の潮流
一眼レフへの未練を捨てきれなかったニコンとペンタックス
2011年カメラ業界では二つの注目の新マウント機が登場します。その一つがPENTAX Qであり、もう一つがNikon 1 V1/Nikon 1 J1でした。
一眼レフで大きなシェアを持っていたニコンと、キヤノン・ニコンの二大一眼レフメーカーに押されてはいたものの、一眼レフ市場でそれなりのシェアを持っており、かつ一眼レフの歴史に大きく関わってきたペンタックスが遂に重い腰を上げてミラーレスに進出してきたのです。
この頃ペンタックスブランドは経営難からHOYAやRICOHといった企業に翻弄されていた部分もあり、内部的にはかなり厳しい開発環境になってきていたことが容易に想像できるのですが、ニコン、ペンタックス共に、FマウントとKマウントという長年の一眼レフマウントへの未練を捨てきれておらず、明らかに未来の主力となれない小口径マウントでミラーレス市場に参入することになります。
Qマウント、Nikon 1マウント共に小型センサーしか搭載することができず、ブランド力からNikon 1は当初こそそれなりに売れたのですが、その後のニコンのフルサイズ対応ミラーレスマウントへの転換にとって大きな足枷となっていきます。
吹き荒れるカメラ女子ブームと翻弄されたメーカーたち
Nikon 1はその当時流行っていたカメラ女子たちに支持されていた「クラカメ風デザイン」に対するアンチテーゼとも言える「ミニマルデザイン(引き算で構成されたシンプルなデザインのこと)」と、当時のミラーレスとしては非常に高速に動作する像面位相差AFに代表される先進性を感じさせる興味深い部分も多分にありました。
しかし当時はまだカメラ女子ブームが続いていたため、オリンパスの「クラカメ風デジカメ」が相変わらず売れまくっていた時期ということもあり、女性的なミニマルデザインは男女共に刺さることはありませんでした。
私個人は若い頃New F-1やF3のようなリアルなクラカメを何台も使い倒してきた世代であったこともあり、当時カメラ女子に評判の良かった、(本物のクラカメには似ても似つかない)クラカメ風デジカメというデザインが大嫌いでした。
そのためミラーレスのPENシリーズのデザイン面だけに対して言えば、ユーザーの方には大変申し訳ないのですが、フィルムカメラのオリジナルPENシリーズの名を借りた偽ブランドのようにしか見えませんでした。
それよりはむしろ新しいことをしようという意欲が見えた初代Nikon 1 V1のミニマルデザインや、ソニーのNEX-7のレトロフューチャーデザインの方に遥かに好感を持っていましたし、特にNEX-7にはソニーらしさという面も盛り込まれていて素晴らしいデザインだと今でも思っています。
とは言えやはり当時爆発的にカメラを買っていたのはカメラ女子であったため、圧倒的に売れていたのはオリンパスでした。
宮﨑あおい+クラカメ風デザインというブンラドイメージは強く、ニコンもミラーレスの先駆者であるパナソニック、そして当時競合他社とのセンサーサイズの違いを必死にアピールし「センサーが大きいから背景をボカせる」といったようなワード(その説明が必ずしも正確ではなかったとしても)なども使って若い女性層にアプローチしようと頑張っていたソニーも含め、売れまくるオリンパスPENシリーズの脇で他メーカーは為すすべがありませんでした。
それほど国内のミラーレス市場ではオリンパスが突出して強かった時代でした。
最初から地獄だったPENTAX Qとビッグチャンスを逃したNikon 1
PENTAX Qに関してはセンサーサイズの小ささを他社ファンから指摘され続け、カメラ女子に対するペンタックスブランドの知名度の低さなどから最初から大苦戦が続きます。
その後数年間PENTAX Qシリーズはカラバリやレンズの低価格路線など懸命の努力をするのですが、正直に言えばQマウントは最初の時点でもうどうすることも出来ない終わっていた規格でした。
この当時吹き荒れていたカメラ女子ブームは女優の宮﨑あおいさんがきっかけとなりましたが、元々宮﨑あおいさんはニコンのフィルムカメラFM3Aなどを使用しており、雑誌のインタビューなどで趣味が写真撮影というようなことも語っていました。
にも関わらず、ニコンがアプローチする前にオリンパスはデジタルカメラのイメージキャラクターとして宮﨑あおいを起用します。
もしこの時ニコンが、
- フルサイズ対応のZマウントで
- クラシックデザインのカメラを
- 宮﨑あおいのCMで宣伝で発売
していれば、その後のミラーレス業界の勢力図は大きく変わっていたことでしょう。
Nikon 1システムは、センサーサイズの小ささと高速なAFを生かして、それまで1DやD一桁シリーズと大口径超望遠レンズという非常に高額にならざるを得なかった野鳥撮影や航空機撮影を安価に撮影可能なシステムとしての期待もありましたが、実際にニコンがNikon 1マウント用の超望遠レンズである1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6を発売したのは2014/06/26ですから数年先のこととなります。
■2012年頃 〜機械計測という新しい評価基準〜

2012年頃を代表するカメラ
ソニー NEX-7/オリンパスOM-D E-M5/ニコンD800/キヤノンEOS 5D Mark III/ペンタックスK-30/ソニーCyber-shot DSC-RX100/ニコンD600/キヤノンEOS M/パナソニックLUMIX GH3/富士フイルムX-E1/キヤノンEOS 6D/ソニーα99/シグマDP1 Merrill,DP2 Merrill,DP3 Merrill
2012年頃のカメラ業界の潮流
カメラ女子ブームからカメラ男子ブームへ
2012年は年初に発売日がずれ込んだNEX-7が発売されました。NEX-7はトライダイヤルナビ(機能を切り替えられるダイヤルでダイヤルに機能表記がない)といった独特の操作系をもっており、それについていけないという声も年配を中心にありました。
このトライダイヤルナビという考え方はデジタル時代にはある程度マッチした方法で私は好きだったのですが、時代が追いついていなかったように思います。
とは言ってもNEX-7はレトロフューチャー的な未来感とクラシカルさ両立したデザインで人気を博し、当時カメラ女子ブームから連なって発生した、言うなれば「カメラ男子ブーム」的なものには良く刺さってヒットしました。
このカメラ男子ブームとは、コシナなどの比較的安価なライカMマウント用レンズをマウントアダプターを使用してミラーレスに使用してクラシック感を演出するというようなハッキリ言って非常にオタくさいブームでした。
- マウントアダプターでクラシックレンズをミラーレスに使う
- 外観をクラカメ風にするために張り革をする
- クラシック風なストラップやジャケットを付ける
というような行為に代表されるカメラ男子ブームは、カメラマニア内ではそれなりに大きなブームだったのですが、カメラ女子ブームのように世間一般にまで拡散していくものではありませんでした。
そもそもフィルムを想定して作られたクラシックレンズの場合、解像力の面だけでなく、画面周辺の不自然な色被りや大きめの周辺減光が発生しやすいため画質的な問題が多く、基本的にはファッション的な意味合いの方が大きかったのですが、それはカメラ女子ブームも似たようなものなので、カメラ男子ブームだけを批判することも不公平といえば不公平なのかも知れません。
何よりも批判されるべきは、その低レベルな流行に殆ど全てのカメラメーカーが便乗しようとしたことであり、本当にカメラ史における黒歴史だと思っています。
ただ、そうしたミラーレス側で起きていたブームとは別のところで、D800やEOS 5D Mark IIIといった長い間プロ・アマに高く評価される優れた機種が登場した年でもありましたことも忘れてはいけません。
DxOに代表されるレビューサイトの一般化
セールスに直結するカメラ女子ブームやカメラ男子ブームが起きていた影で、カメラマニアの中にはある新たな動きが起きていました。
それはDxOセンサーレーティングに代表される、海外のカメラレビューサイトの機械計測によるカメラ・レンズ評価が(カメラマニアの中で)一般化していくという潮流でした。
実はこれは後にカメラ業界の流れを決めることになる大きな出来事で、それまでカメラやレンズの画質評価というと、
- 空気感
- 立体感
- 質感
といったような抽象的な表現が横行していました。
これは必ずしも悪いことではないものの、あまりに非科学的で主観的な評価も多数ありました。
当時日本のカメラ系サイトやカメラ系雑誌は写真家による印象論や抽象的な表現のレビューが一般的な時代で、特に等倍画像を見られない紙媒体などでは、カメラマニアたちはそのレビュアーの「眼力」や「誠実さ」のようなものを信用して機種選びをすることも多い状態でした。
しかしそこにDxO Markやphotozone(現:OpticalLimits)に代表される、イメージセンサーやレンズの性能を機械的に計測し数値化して評価するという海外のカメラ系レビューサイトの方にカメラマニアたちの注目が集まり始めたのです。
こうしたサイトは一部の人は少し前から注目していたものの、カメラマニアの中でもあくまで少数派でした。
それがこの頃になるとこうした機械計測によるレビューがカメラマニアにとってのカメラ・レンズの評価方法の主流になっていきます。
具体的に例えると「DxO見てみたらNEX-7は解像力は上がったけど、NEX-5Nの方が高感度のスコアが高い。APS-Cには1600万画素がベストバランスかも」というような会話がネットのカメラ談義などで一般化し、これはレンズに関しても同様で、初期の頃はphotozone(現:OpticalLimits)などが良くマニアたちに参照されていました。
DxOにせよOpoticalLLimitsにせよ、「カメラやレンズにより具体的で客観的な評価がされるようになった」という意味で良いことなのですが、これによってカメラ評価の中の一部、特にイメージセンサーに対する注目が異常加熱し始めます。
これがどのような問題をもたらしたかということなのですが、メーカー側が幾ら他の部分を作り込んでも、イメージセンサーのスコアでカメラの評価がおおよそ決められてしまうというような問題が起き始めていました。
レンズ開発の実例にみる性能数値化の危険性
あるメーカーのレンズ開発の話をしましょう。
レンズの「歪曲収差」についてはこのようなニッチなサイトを読む皆さんに改めて説明するまでもないでしょう。
詳しく言うとどのレンズか分かってしまうのでボカして話しますが、とある結構高級なズームレンズのテストの時に聞いた話で、そのレンズで素直な設計を行うと「広角側である程度の樽型収差が出る」という状況があったそうです。
そこで歪曲の最大値だけで見れば、樽型ではなく陣笠収差(樽型と糸巻き型が混ざったような波打つような収差)になるように設計した方が、(波型に歪曲が戻っていくので)数値上の歪曲の最大値は少なく出来たそうなのですが、そのレンズの開発者たちはそうした解決法を選択しませんでした。
なぜかというと、実際の使用では陣笠収差よりも素直な樽型収差の方が、
- 現像ソフトにレンズ情報がない場合や純正ボディとの組み合わせでなくても歪曲補正が容易
- 撮影時に歪曲収差の出方の確認がしやすい
といったようなメリットがあるからということでした。
つまり陣笠収差にして数値上の歪曲のパーセンテージを減らすよりも、全体のワークフローを考慮して素直な樽型収差を残す方が良いという判断です。
そもそもこの樽型・陣笠の話はレンズ開発において新しい考え方でもない上、冷静になって考えれば「カタログスペックより実用性を重視すべき」というのは当たり前の話です。
しかしレンズも数値だけで評価されてしまいやすい時代においては、レンズ開発の専門家であってさえ「ネットであのレンズは歪曲の数値が○%だったからダメなレンズ、という悪評が流れて売れなかったらどうしよう。それならいっそ実用性よりも数値重視で陣笠収差に…」という発想が生まれてしまう「可能性」はあるわけです。
このレンズに関しては開発陣が賢明であったことやプロの使用を想定した高級レンズであったこともあり、「このレンズを真に必要とするレベルの撮影者であれば、正当な評価をして貰えるはず」という結論に至り、素直な樽型収差のままそれを抑制するという方向性で開発され、当然私もその開発者の方の考えに賛同しました。
実際は樽型収差も極端なものではなかったのですが、案の定海外の機械計測の有名レビューサイトで、「広角端で樽型収差が出るのが欠点」というレビューがされ光学性能に関して特に高い点数は貰えませんでした。
そうした評価も開発者からすれば想定内であったでしょうし、そもそもレビューしている人たちも日常業務であるわけですから、一つ一つの製品にそこまで深く考察することを求めるのも酷なことだと思います。
ただ機械が出す数値だけを見てレビューしていたのでは当然そうした評価しか出来なくなりますし、レビューを見る側が「樽型収差が大きいのかダメレンズだな」という印象を受けたとしても仕方がないことでしょう。
とは言え実際にそのレンズを購入した人たちは、
- 高級レンズを所有できればそれでいいというだけの人
- 設計思想を理解した上で使いこなせるプロレベルの人
恐らくはこの二種類のタイプしかいないようなレンズであったことから、実際にはこのレンズは発売後の実写評価などを経て、多くのプロ・ハイアマチュアから非常に高い評価を得ることが出来ました。
カメラの評価に対する思想が求められる時代に
カメラやレンズは様々な要素から成り立っているわけで、ボタンやダイヤルの操作感、グリップ、メニュー体系、デザイン、ファインダーの見え味など、人間の感覚的なものでしか評価しにくい部分も多々あります。
そうしたスペックに現れない部分の評価について、以前それらの要素の「ごく一部」ではありますが、話した記事がありますでご興味があれば、「カタログスペックに騙されない、カメラの良し悪しの見分け方」という記事をご覧いただければと思います。
カメラマニアがより適切にカメラを評価をできるようになれば、メーカー側も実用性を追求したカメラ作りが行いやすくなり、その成果は結局はカメラマニアに還元されていくものです。
DxOに代表される機械計測によるレビューサイトの登場によってカメラやレンズの評価は容易になったのではなく、むしろ数値化されにくい部分を適切に評価できる見識を持っているかが問われる時代になってきたのがこの頃からだと思います。
■2013年頃 〜遂に登場したフルサイズミラーレス〜

2013年頃を代表するカメラ
ニコンCOOLPIX A/リコーイメージング GR/キヤノンEOS kiss X7/ニコンD7100/富士フイルムX-M1/オリンパスOM-D E-M1/パナソニックLUMIX GX7/ソニーα7,α7R/ペンタックスK-3/ニコンDf/キヤノンEOS 70D
2013年頃のカメラ業界の潮流
フルサイズミラーレスの始まり
2013年頃のカメラ業界で最も注目を集めた機種はやはり世界初のフルサイズミラーレス機であるソニーα7/α7RとニコンDfだと思いますが、後のカメラ業界への影響という意味では最も語られるべきはやはりα7/α7Rでしょう。
今聞くと信じられないかもしれませんが、α7/α7Rの登場時の評価はそれほど高いものではありませんでした。
待望のミラーレスによるフルサイズ機の登場ではあったものの、初代機となるα7/α7Rは完成度という意味では良いとはいえず、特にシャッターボタンの位置やグリップの出来、マウント強度などの面で批判されることも多くありました。
しかしこの記念すべきフルサイズミラーレスの初代機であるα7/α7Rが登場は、
- Eマウントがフルサイズセンサーに対応していること
- ミラーレスは一眼レフの格下ではなく次世代のレンズ交換式カメラの主役になり得ること
この二つを証明しました。
それまではミラーレスは「ブリッジカメラ」というような呼ばれ方をされていたこともあり、簡単に言えばコンデジと一眼レフの中位のカメラというような立ち位置でした。
しかしα7/α7Rの登場によってミラーレスがレンズ交換式カメラの次代の主役、つまりレンジファインダーから一眼レフ、一眼レフからミラーレスといった流れを明確に示したわけです。
DfとFマウントのニコンにとっての功罪
もう一つこの年の注目機種としてニコンのクラシックスタイルカメラDfがあります。
Dfは当初動画によるティザー広告によって話題になりました。
国内メーカーではキヤノンと並んでもっともクラシックカメラの重厚な歴史をもつニコンからクラシックスタイルのカメラが登場したということで、発売後数ヶ月間に渡ってDfは品薄状態が発生します。
背面がデジタルカメラのパーツを流用していたことや、背面液晶を搭載する必要などの理由から実際のフィルム時代のF3やFM3Aとカメラと比較して分厚かったことなど、細部においてDfはそのスタイルを批判される部分もありました。
しかしDfは基本性能を同等とするD610と比較して当時の最安値で7-8万円ほど高価であったにも関わらず品薄状態が続いたわけで、商売としては一時的には成功したと言えますが、こうしたDfのセールスとしての成功もニコンにFマウントに対する執着を長引かせてしまった要因の一つだったと言えるでしょう。
キヤノンのEFと比較されることが多かったFマウントは、マウント径が小さいといったような弱点はあったものの、様々な細部での仕様変更もありニコンファンでさえ完全に理解することは難しいほどの非常に複雑なマウントになってはしまっていたという問題がありました。
とは言え、Fマウントはなんだかんだで長い一眼レフ時代を乗り切った出来た偉大なマウントであったと思いますが、この所謂「不変のFマウント」というブランドがニコンのフルサイズミラーレスへの進出を遅らせた要因となったことも事実でしょう。
その他のミラーレスメーカーの苦しみ
この頃キヤノン、ニコン、リコー以外のメーカーは既にミラーレスに全力投球していたわけですが、オリンパスはフラッグシップ機であるOM-D E-M1などを投入してはいたものの、α7/α7Rの登場によって、いよいよ多くのカメラマニアの中にマイクロフォーサーズシステムの将来性に対する不安が広がり始めていました。
レンズ交換式カメラが売れた最後の年
実は2013年はレンズ交換式カメラが最も売れた年でした。
この頃既にスマートフォンの影響によってコンパクトデジタルカメラは販売台数を急速に落としていましたが、レンズ交換式カメラまではその影響は届いておらず、レンズ交換式カメラは出荷台数で前年2012年比127.4%(一眼レフ:142.3%、ミラーレス:108.8%)と出荷台数を好調に伸ばしていました。
そのため「コンデジはスマホに食われても、レンズ交換式カメラは大丈夫だろう」という希望的観測をしていた人々もいましたが、当然そのような考えは甘く、翌2014年からはレンズ交換式カメラもスマートフォンの進化とSNS文化のさらなる加速によってどんどんその市場を食われていくことになります。
この頃すでにレンズ交換式もいずれはスマートフォンに侵食され始めるということを予見していた人はそこそれなりにいたと思うのですが、この頃からカメラ業界・カメラマニアの中に、「レンズ交換式カメラが生き残るには、高付加価値のフルサイズミラーレスだ」という間違った認識が広がり始めた時期でもありました。
そのため多くのメーカーがこの頃からソニーを追う形でフルサイズミラーレス(あるいは中判ミラーレス)の開発を始めるのですが、「その程度ではカメラ業界の衰退は止められない」というシビアな現実に誰もが気付くのはもっと先の話となります。
■2014年頃 〜レンズ交換式カメラまでもがスマホの餌食に〜

2014年頃を代表するカメラ
富士フイルム X-T1/ソニーα6000/パナソニックLUMIX GH4/ニコンNikon 1 V3/シグマdp2 Quattro/ペンタックス645Z/ニコンD810/パナソニックLUMIX GM5/キヤノンEOS 7D Mark II/富士フイルムX100T/ソニーα7 II,α7S
2014年頃のカメラ業界の潮流
徹底改善されハイアマのフルサイズミラーレス移行を予感させたα7 II
2014年頃発売された機種で後のカメラ業界に大きな影響を与えたものといえば、ひとつは初代機α7から一気に完成度を上げ、ニコン・キヤノンのフルサイズ機と十分に戦えるようになったα7 IIでしょう。
そしてユーチューバーに代表される自撮り一眼動画ブームとも言える新しい市場に刺さったパナソニックLUMIX GH4であったと思います。
それまでフルサイズミラーレスという「コンセプト」に対するカメラマニアたちの期待は高かったものの、初代機であるα7/α7Rは、同時期に発売されていたキヤノンのEOS 5D Mark IIIやニコンのD800のようなトップクラスの完成度を誇る一眼レフフルサイズ機のレベルに達していないことは明らかでした。
しかしこのα7 II、そして翌年に発売されるα7R IIをもって、それまでニコンやキヤノンのフルサイズ機を使用していたハイアマチュアの中にEマウントへの移行を検討する動きが始まります。
それまでソニーにはイメージセンサーに対しての評価は非常に高かったものの、それを支えられるレベルのボディやレンズラインナップがありませんでした。
しかしα7 IIとα7R IIの登場とともに、この頃からソニーのフルサイズ対応レンズラインナップが顕著に充実していき、そのレンズ性能も目覚ましい進化を果たしていきます。
AマウントとEマウントの二股をかけていたソニーが、Eマウントに開発リソースを集中させたこともEマウントにとって良い結果を生みました。
また当時ニコンD3あたりから徐々に始まった高感度耐性ブームのようなものがピークに達した時期であり、一部カメラマニア達の「高画素は要らない、低画素の高感度耐性特化型カメラが欲しい」という要望があったのですが、それに応える形で登場したα7Sは期待通りの圧倒的高感度性能を見せつけ、そうしたマニア達からも大きな支持を得ました。
そしてα7 II/α7R II/α7Sが揃ったことで、(完全に同じわけではではないものの)基本的なデザインや操作性を統一した形で、
- 中庸で中核となる中画素フルサイズ→α7シリーズ
- 高解像で高級な作りの高画素フルサイズ→α7Rシリーズ
- 高感度に優れた低画素フルサイズ→α7Sシリーズ
というイメージセンサーの特性を利用して差別化を図る「α7というくくりの中で横のシリーズを構成する」という、ソニーならではのラインナップ構成を確立した時期でした。
この通常の上級機・中級機・初級機と行った縦軸とことなる横軸のラインナップ展開は、それまでもキヤノンのEOS-1D/EOS-1Dsシリーズ、ニコンのD一桁/D一桁Xといった一部の機種では存在していましたが、中核機種でかつ3種類も展開するというのは珍しいものでした。
ユーチューバーを主体に自撮り動画需要に嵌ったLUMIX GH4のコンセプト
もう一つこの頃の重要な機種の一つとしてLUMIX GH4を取り上げたいと思います。
LUMIX GHシリーズはLUMIX Gシリーズのハイエンド機として2009年から登場し、もともと一眼動画機としても強いシリーズで一部プロや動画ユーザーがCMやMVなどの映像制作で使用するといったことはあったものの、あくまでもニッチな需要を満たす機種であり一般にヒットしていたわけではありませんでした。
しかしこの頃からYouTubeが世間的に大きな注目を集め始め、有名ユーチューバーたちが登場し、そうしたユーチューバー達が、
- プロ並みの高画質
- いわゆる「30分縛り」がない
- 動画のプロではないユーチューバーでも扱える
- 自撮り撮影に強い
というユーチューバーの使い方に適合したカメラを模索しはじめます。
その結果、それらの要素を全て踏まえていたLUMIX GH4を有名ユーチューバーがこぞって使い始め、それを動画でレビューした結果、それに影響され画質にこだわるユーチューバーたちもLUMIX GH4を使い始めるという流れが生まれ始めました。
そのニーズに気付いたパナソニックは、どうすればLUMIX Gシリーズが生き残れるのか?といった苦悩の中、GHシリーズに関しては一筋の光明を見出すことになります。
もちろんLUMIX GHシリーズによるユーチューバー用途だけでLUMIX Gシリーズの事業が生き残れるわけはなく、後のLUMIX Sシリーズの開発へと繋がっていくのですが、それまで存在はしたものの常にニッチであった「一眼動画」という市場が、この頃からユーチューバーを中心に、ある程度一般に近いクリエイターにまで拡大していきました。
一昔前までは動画マニアでもない一般の人、やましてや例えば「ホワイトバランス」といった言葉すら知らないごく普通の若い女性が一眼動画を勉強するなどということはありえなかったことですが、そうした女性層さえも有名ユーチューバーに影響されてLUMIX GHシリーズなどを使い、ライティングを組んで高画質な動画をバンバン投稿していくという光景には本当に驚かされました。
勿論ユーチューバーが必ずしもLUMIX GHシリーズだけが利用されていたわけではなく、(自撮りができる必要があるため)EOSのバリアングルモニター搭載機やαのAPS-C機なども使われていたのですが、それまでよりも圧倒的に広い層に一眼動画を普及させた火付け役となったのがLUMIX GH4だったというわけです。
■2015年頃 〜加速するソニーの技術力〜

2015年頃を代表するカメラ
オリンパスOM-D E-M5 Mark II/キヤノンEOS M3/ニコンD7200/富士フイルムX-T10/キヤノンEOS 5Ds,5DsR/シグマdp0 Quattro,dp1 Quattro,dp3 Quattro/パナソニックLUMIX GX8/オリンパスOM-D E-M10 MarkII/ソニーα7R II,α7S II
2015年頃のカメラ業界の潮流
ソニーの技術力を見せつけたα7R II
2015年にインパクトを残したカメラとしてはα7R IIやEOS 5Ds/5DsRなどがありますが、EOS 5Ds/5DsRはヒットしたニコンD800シリーズに代表される(当時の)他社超高画素機モデルに対抗する機種とした登場した流れであり、それなりに売れましたが、EOS 5Ds/5DsR自体がその後のカメラ業界に大きな影響を与えたとか新しい潮流を作った機種とは言えないでしょう。
2015年に登場したモデルで最も強いインパクトを残したのは、「ミラーレスの構造上の利点」と「ソニーのイメージセンサー技術」という二つの要素が融合した際のポテンシャルの凄さ感じさせたα7R IIでしょう。
α7R IIは有効約4240万画素の世界初フルサイズ裏面照射型CMOSセンサーは、高解像と高感度耐性というそれまで二律背反と思われてきた二つの要素と両立し、当時としては突出した性能を誇るイメージセンサーとして強烈なインパクトを残しました。
2019年現在でさえこのα7R IIを超えるフルサイズイメージセンサーは数えるほどしかなく、今でも十分に通用する画質を誇っています。
また世界最多399点像面位相差AFセンサーを高密度に配置した広いAFカバー範囲もカメラマニア達を震撼させました。
この広範囲にわたる超多点測距は一眼レフでは構造的に実現するのが難しく、また単にミラーレスであればどのメーカーでも実現できるというものでもなかったため、イメージセンサーの性能とも合わせてソニーの技術力の高さをカメラ業界に示すとともに、カメラマニアの一部のカメラマニアたちのソニー信仰の始まりのきっかけともなりました。
実際はα7R IIもその後のα7・α9シリーズも必ずしも実際の連写撮影時に他社競合機と比較して合焦率が高かったわけではありませんでした。
その理由として現実のAF-Cの連写では、
- AF-Cで被写体を追って表示しているだけの状態
- 実際にシャッターを切って一時的に被写体の位置情報が遮断されて再度被写体を補足する必要がある場合
この二つでは1と2で条件が異なるため、単純に超多点で被写体を追うことが出来るという処理速度とは別に、シャッターを切って被写体情報が一旦遮断された後の次の被写体の位置の予測するアルゴリズムが優れている必要があります。
そのため、単にライブビューでの測距処理が他社より速いというだけでは連写時の実際の合焦率までは高めるのが難しかったのではないか?と思っていますが、これはあくまで私の想像であって本当のところは分かりません。
しかし店頭でちょっと触った場合やYouTubeなどの比較的ライトなレビューでは、α7R IIのAF-C時における画面の広範囲に対して爆速で追いまくる測距点の動きはカメラマニアたちを驚嘆させるに十分なものでした。
被写体へのAFの追随速度自体は同時代のキヤノンのEOS-1D系やニコンのD一桁系を使っていた人なら驚くほど高速なものではなかったのですが、α7R IIの場合、
- 画面の広範囲に対して被写体を追える
- 大きな背面液晶のライブビューでそれを見られる
という一眼レフ機にはない視覚的な確認しやすさと、かつそれを人に伝えやすかったためカメラマニアたちに強烈な印象を残すことに成功したように思います。
ひっそりと動画用途でプロに広がり始めたα7R II
動画性能においてもα7R IIは非常に高い画質を有していましたが、このαのフルサイズミラーレス一眼動画というコンセプトはアマチュアというよりもプロ受けが良く、フルサイズセンサーの動画機としてはシネマカメラと比較すると遥かに安価かつ軽量であったことから、導入コストとオペレーションの容易さの両面からα7R IIはさまざまなプロの動画撮影の現場で利用されていくようになります。
この頃、先に説明したように自撮りが重要になるユーチューバーたちにはLUMIX GH4の流行がさらに加速していたのですが、その裏側でプロユースではα7R IIが一眼動画機としてのシェアを拡大していました。
プロたちはそもそも自撮り用途ではないこと、また基本的に30分を超える長回しをすることがないために、LUMIX GH4よりイメージセンサーの大きいα7R IIの方が選ばれやすくなっていったのです。
これは2019年時点でも同じで、現在一眼動画機として一番プロに使われているのはおそらくα7R III(※α7R IVは登場してまだ間もないため)でしょうし、これはコマーシャル・フォト(広告写真のプロフォトグラファー向け雑誌)誌の2019年2月号の「フォトグラファー白書」の調査でも同様の結果が出ています。
ただこの動画用途に関してですが、動画品質にこだわるユーチューバー達の現在の主流は依然としてLUMIX GHシリーズですし、またパナソニックからLUMIX S1R/S1Hのようなフルサイズかつ強力な動画性能を有するライバルが登場したことで、今後のプロユースの動画用途では、α7RシリーズとLUMIX S1R/S1Hシリーズの熾烈な争いが予測されます。
■2016年頃 〜打つ手がなくなったオリンパスの凋落〜

2016年頃を代表するカメラ
オリンパスPEN-F/富士フイルムX-Pro2/キヤノンEOS 80D/ニコンD5/ペンタックスK-1/パナソニックLUMIX GX7 Mark II/キヤノンEOS-1D X Mark II/ニコンD500/富士フイルムX-T2/キヤノンEOS 5D Mark IV/シグマsd Quattro,sd Quattro H/オリンパスOM-D E-M1 Mark II/ソニーα99 II/ソニーα6500
2016年頃のカメラ業界の潮流
オリンピックイヤーを飾った一眼レフの高級機達
この年2016年は夏季オリンピックの開催年ということもあり、ニコンがD5とD500、キヤノンがEOS-1D X Mark IIとEOS 5D Mark IV、リコーがK-1と高級機をこぞって発売し話題になりましたが、逆に言えばこの年が一眼レフが華やかに咲き誇った最後の年ともなりました。
D5とD500は高性能な新型のAFモジュールを搭載し、EOS-1D X Mark IIやEOS 5D Mark IVは人気モデルをブラッシュアップさせ、ニコン・キヤノン共にプロ機の面目躍如とも言える一眼レフをリリースします。
そしてリコーもK-1というペンタックスユーザー待望のフルサイズ一眼レフを、実にペンタックスらしいコンセプトで世に送り出し、台数こそそれほど伸びたわけではないものの、ペンタキシアン(※ペンタックスの熱烈なファンのこと)たちにとってのビッグプレゼントとなりました。
かつての大成功に足を引っ張られたオリンパス
一眼レフ陣営がD5やEOS-1D X Mark IIというフラッグシップやEOS 5D Mark IVという元々完成度の高かったカメラをさらに磨き上げたり、長年ファンを待たせた待望の機種となるD500やK-1をリリースしていた傍で、技術力でリードしていたソニーを除くミラーレス陣営にとって2016年は迷走を極めた一年となりました。
オリンパスはPEN-FとOM-D E-M1 Mark II、富士フイルムはX-Pro2とX-T2、パナソニックはLUMIX GX7 Mark IIといった機種をリリースしましたが、いずれも今ひとつインパクトにかける機種でした。
それぞれのカメラは悪いカメラではなかったものの、ニコンD5やキヤノンEOS 5D Mark IVのような歴史の積み重ねからくる圧倒的な完成度の高さをみせるわけでもなく、ソニーのような革新性を感じさせるものでもありませんでした。
ソニーは「イメージセンサーを主軸にした先端技術力で独走する」というαの明瞭なコンセプトを打ち立てるのに成功していた傍で、その他の当時のミラーレス陣営(オリンパス、パナソニック、富士フイルム)たちは、どの方向に舵を切れば生き残れるのか?を模索していた時期でした(※もちろん開発しているメーカー側はもっと先に新マウントの開発を始めているわけなので、これはカメラマニア側、つまり外側から見た場合の話です)。
しかしパナソニックは社内的にはLUMIX Sシリーズの開発、富士フイルムは翌年に登場する中判ミラーレスGFXとXシリーズの二本柱でいくという次の展開があったわけです。
そうした中、最も厳しい状況に立ちつつあったのはリコーと、「かつての」ミラーレスの覇者であったオリンパスでした。
ユーザーの方には申し訳ないのですが、PEN-Fはとうに過ぎ去ったカメラ女子ブーム時代の栄光が忘れられないとしか思えないデザイン頼りの明らかな凡作で、「オリンパスに次の手が思い浮かんでいない」ということをむしろ証明してしまうような機種でした。
OM-D E-M1 Mark IIも単体で見れば決して悪いカメラではありませんでしたが、ソニーがフルサイズミラーレスを続々投入する中、フォーサーズセンサーでフラッグシップと言い張らざるをえないというのは、カメラマニアに対していかにも弱々しい印象を与えてしまう結果となりました。
かつてカメラ女子ブームで圧倒的な人気を誇ったオリンパスは、その一時の成功のためにパナソニックのようにフルサイズへの移行を決断できず、マイクロフォーサーズへの未練を断ち切ることが出来ずにいました。
「失敗は成功のもと」とは良く言われますが、実は「成功は失敗のもと」でもあり、流行に敏感でうつりげな若い女性層をターゲットに売れまくったカメラ女子ブームでの成功はのちのオリンパスの失敗のもとになってしまったわけです。
そうした意味で2016年は一眼レフ最後の百花繚乱と、ミラーレスでのソニーの独走、その他のミラーレス陣営の混迷を極めた一年だったと言えるでしょう。
■2017年頃 〜一眼レフの到達点とミラーレスへの転換点〜

2017年頃を代表するカメラ
リコーPENTAX KP/富士フイルムGFX 50S/パナソニックLUMIX GH5/キヤノンEOS M6/ニコンD7500/ソニーα9/キヤノンEOS 6D Mark II/ニコンD850/ソニーCyber-shot RX10 IV/富士フイルムX-E3/オリンパスOM-D E-M10 Mark III/パナソニックLUMIX G9/ソニーα7R III
2017年頃のカメラ業界の潮流
ハイクオリティを実現したD850とそれゆえに見え始めた一眼レフの到達点
この年ニコンはD850という人気シリーズのフルモデルチェンジを行いました。
このD850はその当時ニコンの持てる一眼レフ技術の全てを投入したと言える傑作で、その高いクオリティもあって市場の評価も上々でした。
恐らくデジタル一眼レフの歴史の中で最高到達点となるのは今後登場するフラッグシップであるニコンD6とキヤノンEOS-1D X Mark IIIとなるでしょうが、D850もまたフルサイズ上級機の一つの完成形と呼べるものでした。
しかし、それゆえに一眼レフの到達点が見え始めた機種でもありました。
報道用プロ機の市場に進出し攻勢を仕掛けたソニー
この頃は各社がミラーレスのラージフォーマットへと注力していくことは誰の目にも明らかになり、キヤノン・ニコンといった規模を必要とするメーカーはソニーを追う形でフルサイズミラーレスへ、富士フイルムはブルーオーシャン(競争の少ない未開拓市場)である中判ミラーレスに踏み込んでいくのが想定されました。
確実に来るであろうキヤノン・ニコンのフルサイズミラーレスに対する注目は非常に高かったのですが、それに対して先手を打つようにソニーはα7R IIIでα7シリーズを強化し、さらに待望のフラッグシップ機であるα9を投入、それまでキヤノン・ニコンがお互いしか競合がいなかった報道用プロ機市場に打って出ます。
αシリーズ全体のラインナップという意味で考えれば、当然α9の投入によってラインナップは増し、α9と組み合わせるための大口径超望遠レンズも増やしていくという雰囲気を出すことに成功したわけで、αシステムの充実という点においてα9をリリースした意味はソニーにとって非常に大きなものでした。
α9の撮影領域のほぼ全面となる約93%をカバーする693点の像面位相差検出AFセンサーは、従来の一眼レフのボディ下部AFモジュールでは実現が難しいもので、かつ電子シャッター時に限定されるとはいえ秒間20コマという連写速度もクイックリターンミラーの動きが必要な一眼レフを圧倒する速度でした。
ただ当時Eマウントに大口径超望遠レンズが充実していなかったことやα9自体の報道用プロ機としての作りの甘さに加え、ソニーのスチールカメラでの報道用プロ機の歴史やプロサポートの弱さなどからくる不安点を払拭出来ていなかったため、翌2018年のモスクワサッカーワールドカップではα9の姿はほとんど見られず、相変わらずEOS-1D X Mark IIやD5といった機種ばかりが並んでいました。
しかし「売れないものは作らない」という姿勢はかえってシステム全体を弱体化させてしまうため、今のソニーには「プロにどれだけ相手にされなくても、何十年でも報道用プロ機と大口径超望遠レンズを作り続けてやる」という気概が求められています。
ブルーオーシャンへ船出した富士フイルム
ソニーがキヤノン・ニコンが追いつけないように先行逃げ切りを図ってα9やα7R IIIといった意欲的なフルサイズミラーレスを投入していく傍で、富士フイルム、パナソニック、オリンパス、リコーといったメーカーは悩ましい決断を迫られることになります。
イメージセンサーの圧倒的な技術力と先行の利を見せるソニーに加えて、長年築き上げたブランドと開発力をもつキヤノン・ニコンがフルサイズミラーレス市場に進出していくことが目に見えている状況で、同じフルサイズミラーレス市場で後発で勝負して戦えるのか?という問題が富士フイルム、パナソニック、オリンパス、リコーにはありました。
その中で富士フイルムは従来のXマウントにはフルサイズセンサーは入らず、新マウントでフルサイズを出してしまったのでは、せっかく育てたXマウントを切り捨てるつもりだというイメージを持たれかねませんでした。
そこで富士フイルムは新マウントでのAPS-C+フルサイズの二本立てではなく、APS-C+中判という新しい組み合わせに活路を見出します。
中判ミラーレスのGFX 50Sを投入した富士フイルムですが、中判センサー機としては価格はかなり抑えられていたものの、それまでのユーザーの蓄積などの問題も含めて台数的にはそれほど売れたわけではありませんでした。
しかし少なくとも富士フイルムは、大型センサー搭載ミラーレス時代(というよりもマニアしかカメラを買わなくなる時代)に対して、実際に生き残れるかどうかは別として富士フイルムなりの生き残り策を示すことに成功しました。
■2018年頃 〜ついに登場したZとRF〜

2018年頃を代表するカメラ
ハッセルブラッドX1D/キヤノンEOS Kiss M/富士フイルムX-H1/リコーPENTAX K-1 Mark II/シグマsd Quattro H/ライカSL(Typ 601)/ソニーα7 III/富士フイルムX-T3/ニコンZ 6,Z 7/キヤノンEOS R/富士フイルムGFX 50R
2018年頃のカメラ業界の潮流
待望のニコン・キヤノンのフルサイズミラーレスの登場とその評価
2018年、遂にニコンがZ 6/Z 7、キヤノンがEOS Rという新マウントでフルサイズミラーレス市場への進出を開始します。
ただし当初このZ 6/Z 7とEOS Rは機種としての評判は高くなく、両機ともフルサイズ機でありながらシングルスロットであることや、Z 6/Z 7に関しては瞳AFの非搭載(のちにファームウェアアップにて対応)、EOS Rはマルチファンクションバーの使い勝手の悪さなど、先行するα7 IIIと比較されその評価の多くはZ 6/Z 7とEOS Rに対して否定的なものでした。
ただ先にも書いたようにカタログスペックといった表層だけをみてカメラを評価することは出来ないのですが、少なくともカタログスペックにおいてはZ 6/Z 7やEOS Rよりもα7 IIIの方が優れている部分も多かったことから、当時こうした評価が下されてしまったことは致し方ない部分だったのかもしれません。
悩ましいマウント径とフランジバック長の選択
対するキヤノンとニコンはZ 6/Z 7とEOS Rにおいて、ZマウントとRFマウントのEマウントに対するマウント内径の大きさを積極的にアピールすることで対抗しました。
ソニーのEマウントはマウント内径がフルサイズに対してギリギリのサイズであったため、かろうじてボディ内手振れ補正を搭載出来たもののマウント規格の将来性に対する不安があったことから、キヤノン・ニコンはRF及びZマウントの内径の大きさを積極的にアピールしていました。
これだけを見ると単なるキヤノン・ニコンによるソニーに対するネガティブキャンペーンなのですが、ソニーはソニーでこれまで「○○市場において○○を抜いてフルサイズシェア1位に」といったタイプの、キヤノンやニコンに対するあからさまな当てつけとしか思えないアピールを行なっていたわけですから、当然後発の新マウントであるRFとZマウントはEマウントの弱点であるマウント径の小ささを突いてくることは必然であり、キヤノン・ニコンからすれば「先に喧嘩売ってきたのはソニー」という気持ちでしょう。
またニコンの場合は何年もの間FマウントをキヤノンのEFマウントと比較され続け、その内径の小ささに由来するレンズ開発の不利を指摘されることも多かったことから、新しいZマウントでフルサイズミラーレス用マウントとしては最大となる内径や超ショートフランジバックをアピールすることは、ニコン自身に対するネガティブイメージを払拭するという意味においても自然な流れだったと思います。
対するソニーはソニーで「Eマウントでも大口径レンズの開発は可能」といったアピールもしていますが、レンズマウントはレンズ交換式カメラの基幹要素でもあるので、Eマウントの内径の小ささが将来に対する足枷となる可能性は否定できません。
ただしフランジバックに関しては、
- Zマウント:16mm
- Eマウント:18mm
- RFマウント:20mm
という違いがどのように今後影響するかについて未知数です。
最も短いZマウントと最も長いRFマウントでも4mmしか違わないこのフランジバック長ですが、これは必ずしもどれがベストとも言えないため、この差をどう活かし時にどう補うか各社の構想力がポイントとなりそうです。
特にZとRFのフランジバック長の違いはとても興味深いのですが、両メーカーとも確信を持って「このフランジバック長がベスト」と考えているというより、相当悩んだ末の手探りの決断のように見えます。
いずれにせよ、私はZとRFどちらのマウントも結構期待できる規格だと感じていています。
新マウント採用を決断したキヤノン
またキヤノンのRFマウントについてですが、EF-Mマウントは(電子接点などは考慮しない)内径が47.00mmであり、これはEマウントの46.10mmよりもわずかに大きく、またフランジバックはいずれも18.0mmと同じであるため、物理的にはEF-Mマウントもフルサイズセンサーも搭載は可能に思うのですが、キヤノンは「EF-Mマウントのままフルサイズミラーレスを投入する」という方針は取らず、新マウントを開発したわけです。
EOS Mが登場した2012年にキヤノンの開発者がデジカメWatchのインタビューで以下のような話をしたことは有名です。
“デジカメWatch:EF-Mマウントは例えば35mmフルサイズセンサーなど、APS-Cサイズよりも大きなセンサーにも対応できますか?
キヤノン開発者:それはできないと思います。相当おかしなことをやれば物理的に入らないとは言いきれませんが……。周辺光量が相当落ちるとか、像がどうなるかわからないといったレベルですね。”
なんにせよキヤノンは「フルサイズは新マウントでいく」という決断をしたわけで、これはキヤノンがかつて批判されながらもFDマウントからEFマウントへの転換をおこない、結局はそれが長期的には良い決断であったということも影響していたのかも知れません。
しかし勿論RFマウントでもAPS-C機は作れるため、EOS Rシステムの登場によって「何か特別な用途を見出さない限り、EOS Mシステムは将来的には切り捨てざるを得ないだろう」ということを多くの方に感じさせることとなりました。
富士フイルムの決断
ちなみにそれらトップ3の熾烈な争いの陰で、富士フイルムはレンジファインダースタイルの中判ミラーレス、GFX 50Rを投入、中判ミラーレスのGFXシステムにおいてもAPS-CのXシリーズのキャラクターを引き継ぐという方向性を打ち出してきました。
これはこれで富士フイルム内で「GFXをどういうシリーズにしたいのかがハッキリと見えている」という印象を富士フイルムファンに与えたのではないかと思います。
■2019年頃 〜ソニーの失速とタイタニックと化したカメラ業界〜

2019年頃を代表するカメラ
ニコンCOOLPIX P1000/オリンパスOM-D E-M1X/リコーGRIII/キヤノンEOS RP/ソニーα6400/パナソニックLUMIX S1,LUMIX S1R,LUMIX S1H/富士フイルムGFX100/ソニーα7R IV/ソニーα9 II/シグマfp/ニコンZ 50/富士フイルムX-Pro3
2019年頃のカメラ業界の潮流
ここ数年業界をリードしてきたソニーの停滞
2018-2019年になると「カメラ業界の衰退は底を打つどころかもう底なし沼のような状況である」という絶望感が広がり始めます。
2014年から2019年に至る約5年間、カメラ業界を牽引してきたのがソニーであることは誰もが疑わないところで、特にイメージセンサーの技術力は突出しており、画質と機能の両面でカメラ業界に多大な貢献をしてきたと言えます。
しかし2019年に来て、これまで圧倒的な革新を見せてきたソニーの技術力に停滞の兆しが見え始めます。
2019年に発売されたα7R IVもα9 II、あるいはその他のAPS-C機も正常進化はしていたものの、カメラマニアたちをこれまで驚嘆させてきたソニーらしい先進性を感じさせるものではありませんでした。
またここ数年ソニーに熱狂していたカメラマニアたち自身が、最近はこれまでソニーが得意としてきた「DxO的な数値化しやすい価値観」に対する熱が冷めてきたように思います。
あるいはカメラの進化や自身の学びの中に「新しい価値観」を求めているのかも知れません。
結局のところ、ここ数年ソニーの躍進はかつてのカメラ女子ブームによるオリンパスの躍進と本質的に同じことで、
| メーカー | オリンパス | ソニー |
| 客層 | 若い女性 | カメラマニア |
| 流行の下地 | 宮﨑あおいの写真趣味 | DxO Markの日本での認知 |
| 流行の始まり | ミラーレスの誕生 | フルサイズミラーレスの誕生 |
| 起きた流行 | カメラ女子ブーム | フルサイズミラーレスブーム |
| 支持の理由 | オリンパスのデザイン | ソニーのセンサー技術 |
| 結果 | オリンパスの躍進 | ソニーの躍進 |
こういった要素が重なり合って起きた一時的なブームであり、既にソニーが火付け役となった「フルサイズミラーレスへの移行」という熱狂自体が下火になってきています。
止まらないカメラ業界の衰退
そうしたここ数年業界を牽引してきたソニーの停滞の陰で、というよりも表で、スマートフォンによってレンズ交換式カメラ市場も次々と侵食され、誰もそこから逃れることは出来ませんでした。
ソニーの躍進も結局はカメラマニアが騒いだ程度のものだったので一般にまで波及する規模のものではなかったわけで、キヤノンやニコンといった大御所メーカーがフルサイズミラーレスを投入してもやはりカメラ業界内の一時的な話題で、全体が急速に沈んでいるという事実は疑いようがありません。
今カメラメーカー間で行われている競争など、世間から見れば全く完全に意味のない内紛に過ぎないでしょう。
また現状どのメーカーも、これ以上(我々がいうところの写真機としての)カメラ事業に投資するメリットを感じてもいないように見えます。
パナソニックもフルサイズミラーレスに参戦
またこの年、パナソニックもスタンダードなLUMIX S1、高画素のLUMIX S1R、動画撮影用途のLUMIX S1Hによってフルサイズミラーレスへの進出を果たしましたが、やはりこれも(カメラ市場を拡大されるほどの)革新性を感じさせるものではありませんでした。
またパナソニックはシグマやライカとのアライアンスもLUMIX Sシリーズのアピールポイントの一つとして大々的に宣伝しましたが、そもそもシグマは基本がレンズメーカーですから、結局は売れているマウントを無視できません。
つまり「シグマは今後Lマウントレンズしか発売しない」というのならともかく、実際は売れているマウントならアライアンス外のマウント向けにもレンズを作らざるを得ないわけで、またライカはそもそもパナソニックとは客層も価格帯も違いすぎるために、この3社のアライアンスは少なくともカメラ購入者に対するセールスポイントとして大きな効果を期待できるようなものにはならないでしょう。
そのような状態、つまりどのメーカーもカメラ業界の凋落に対する解決案を示せないまま2019年は過ぎようとしています。
■2020年以降 〜写真文化とカメラの変遷〜
カメラ業界を救う術は…もうない。
衰退が止まらないカメラ業界ですが、これはフィルム時代の規模に戻るとかそういったぬるい話ではなく、カメラ趣味というものが極めてニッチなレベルにまでなるということです。
プロや一部のマニアが残るので写真機としてのカメラが完全になくなるとは思えませんが、カメラ趣味は今後「とてつもなくニッチな趣味」にはなってもおかしくないでしょう。
スマートフォンのカメラ機能やアプリの進化の凄まじさは皆さんもご存知だと思います。スマートフォンのカメラ機能をあくまでも付加価値として搭載しているのにも関わらず、
- 誰にでも
- 簡単に
- 綺麗に撮れて
- すぐシェアできる
というユーザーのわがまま極まりない要望に徹底的に応えてきました。スマートフォン本体とアプリケーションの連携によって本当に「徹底的に」応えてきたのです。
対して専用機であるカメラメーカーとカメラマニアたちの姿勢はどうだったでしょう?
- カメラは勉強して使いこなすもの
- 高い機材が必要
- 写真の勉強もしろ
- いい写真が撮れないのはお前が下手なだけ
このような思想が横行していたではありませんか。
写真専用にも関わらず、スマートフォンよりも写真を撮ることに対してユーザーフレンドリーでないことを誇るような世界を一般人が支持するわけがありませんし、新規客を取り込めなくなった業界が衰退するのも必然でしょう。
それでも、この10年はカメラ業界が史上最も盛り上がり、そして最も急速に衰退した10年であったことは間違いありません。
その歴史的10年間を経験できたことを、カメラ業界の繁栄と滅びの時代を体験できたことを、カメラ好きとして喜ぶべきなのかも知れません。
それでも写真文化は無くならない
写真文化は既にSNSを中心にしたコミュニケーションツールへと完全に移行しています。
カメラやレンズを語る時代は終わりました…
写真作品を語る時代も終わりました…
しかし人々のコミュニュケーションツールとして、写真はこれからも生き続けるでしょう。だからもうカメラなんて一般人には必要ないのです。
スマホで十分だから?…いいえ、違います。
“多くの人にとってスマートフォンこそカメラそのものだからです”
今やカメラ=スマートフォンのことなのであり、それは本当にそのままの意味でそうなのです。その点においてカメラ業界もカメラマニアも認識が甘すぎます。
若い人の中には「生まれてから一度も(我々の言うところの)カメラに触ったことがない、スマートフォンでしか写真を撮ったことがない」という人など山ほどいるのです。
そしてそうした人たちが歳をとり、更に若い世代はもっとカメラに触れないのですから、こうした傾向は今後もより広範囲な世代へと拡大していくでしょう。もうカメラは普通の人が使うものではないのです。
例えて言うなら、今の若い人にとっての写真機とは、我々にとっての盆栽とかアマチュア無線とかそういうレベルの趣味と言っても過言ではありません。
だから我々は、
アジアの端の島国で、
写真文化の隅っこで、
かつては「カメラ」と呼ばれていた特殊な映像記録装置のことを、これからも語っていくのでしょう。
しかし逆にそうした特殊な機械であることが、
- 撮影へいく意欲
- 被写体を探す観察
- より良く撮ろうという集中力
などにつながってもいるわけで、そうした我々が言う所の写真機が持つ高揚感を一般の人に伝えていくことが出来たなら、再びこの業界が光を浴びる日も来るかもしれません。
それも99.9%くらい無理なことだと思いますが、結局それ以外に細々とでも生き残る道はないのです。
Reported by 正隆
